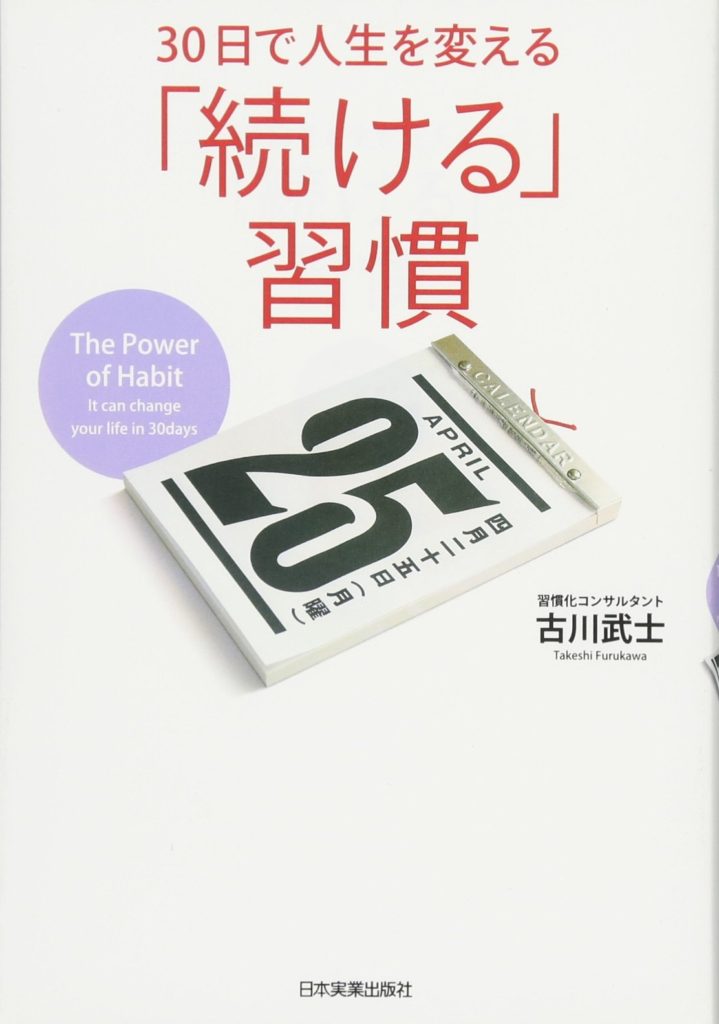概要
習慣化とは「自分が続けたいと思っていることを、意思や根性に頼らず、毎日のハミガキのように楽々続く状態に導くこと」です。
→ この「習慣化」の方法を説いているのが本書。
習慣化に対する考え方
心理学的なアプローチ
逆境に負けないしなやかな力
習慣化するのに必要なことに「やり抜く力(GRIT)」の概念も重要。
なぜ、「習慣化」が必要か?
理由は、私たちが意識して行えることには限界があるからです。
心理学でも、人の行動の95%は無意識によるものであると言われており、無意識のほとんどは習慣でできているのです。
ここで大切なのは、脳にとって、よい習慣、悪い習慣の区別はないということです。
脳からすると、ただ一定期間繰り返されたから習慣化しただけ。よい習慣でも、悪い習慣でも身についてしまいます。
では、なぜ習慣化できないのか?
人間には「新しい変化に抵抗し、いつもどおりを維持しようとする傾向」があるからです。
「一定期間繰り返されたから習慣化しただけ」という箇所との整合性に疑問があります
習慣化のレベルを三つに分類
- 行動習慣:日々の日課や行動習慣(例:勉強、日記、片付け、節約、家計簿など ⇒1か月)
- 身体習慣:身体のリズム(例:ダイエット、運動、早起き、禁煙、筋トレなど ⇒3か月)
- 思考習慣:思考・性格に関わるもの(例:論理的思考力、発想力、ポジティブ思考、ストレス発散思考 ⇒6か月)
本書で扱うのは主として「1.行動習慣」に関するもの。
<原則>
- 一つの習慣に絞る「同時にいくつもやらない」
- 有効な一つの行動に絞り込む「行動ルールを複雑にしない」(例:電車の中でのリスニングだけにする)
- 結果より行動に集中する「結果にこだわりすぎない」
<注意>
1.反発期:すぐにやめたくなる
挫折率42% → 最大の難関
1日目〜7日目
- 対策1 ベビーステップで始める=急がない、いっぱいやらない
- 対策2 シンプルに記録する
2.不安定期:予定や人に振り回される
挫折率40%
8日目〜21日目
- 対策1 パターン化する
- 対策2 例外ルールを設ける
- 対策3 継続スイッチをセットする
3.倦怠期:じょじょに飽きてくる
22日目〜30日目
- 対策1 変化をつける
- 対策2 次の習慣を計画する
もしも
1.毎日30分の読書を3年間続けたら
1冊3時間で読むとしても、3年で180冊になります。専門分野に特化して読めば、最高レベルの知識を手にできるのです。
2.30歳から定年まで毎月3万円を資産運用し続けたら
定年までに大きな資産を作れる可能性があります。
最後に「続ける」すごさのわかる本
『木を植えた男」ジャン・ジオノ著(あすなろ書房)