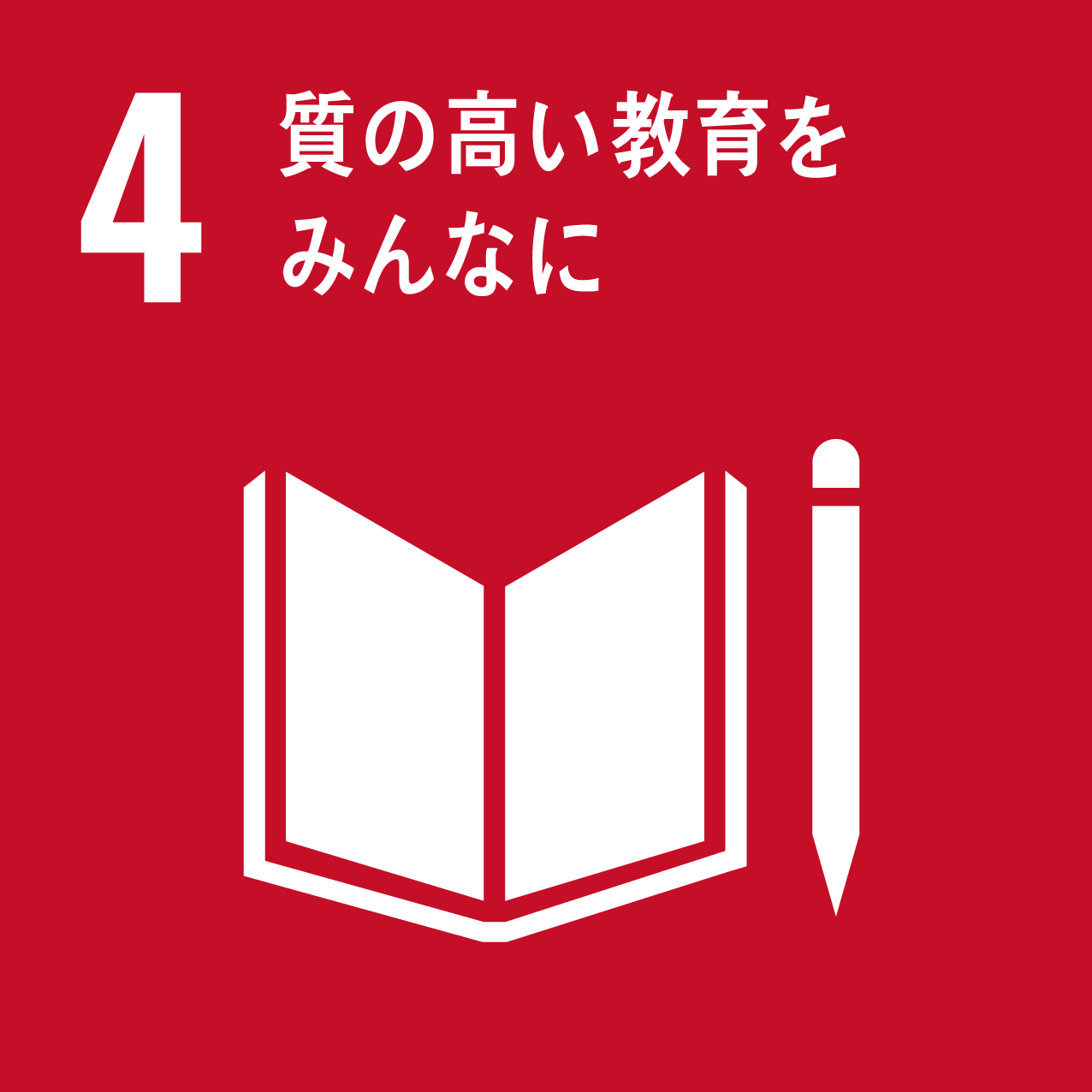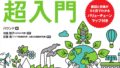目新しい内容ではないです。誰かが、必ず書いている内容ですので、単なるまとめ記事です。
ただただ、子供たちが、時間を気にせず、場所も気にせず、人も気にしないで、必要かつ十分な、個人に合わせた教育が受けられればいいと願っています。
素朴な疑問
現時点の技術で実現できることが数多くあります。技術的な問題よりも、制度や現場がボトルネックになりつつあるようです。
学校という物理的な場所は必要でしょうか?
学校/校舎というのは必須ではないと思いますが、便利だと思います。
しかしながら、好きな場所で教育を受けられる技術があるのに、それを活用せず、認めず、検討しないのは、もったいないです。
学校では経験できない体験をするための機会があるのに、その機会を失うことになります。
例えば、農業体験など、季節が大きく影響する仕事は、体験できるタイミングが重要ですが、物理的な校舎への通学が前提になってしまいますと、せっかくのチャンスを逸することになります。
学校の始業時間、就業時間は必要でしょうか?
子供によって、朝に強い子/弱い子がいます。
また、年齢によっては生理学的に、朝は弱い世代もいます。
それを十把一絡げで同じ時間に教育することに意味はないと思っています。
特定の先生に教わる必要はあるでしょうか?
教えるのが上手な人から教わってほしいと思っています。
例えば、受験予備校のカリスマ的な講師の映像の方が、学校の先生よりもはるかに教育効果が高いのではないでしょうか。
自分で調べるのが好きな子は、時間的な制約を受ける授業よりも、タブレット学習の方がいいのかもしれません。
中室牧子氏の「「学力」の経済学」によると、教員免許の有無による教員の質の差はかなり小さいというのがコンセンサスだそうです。
そして、教員の質は子供の将来に大きな影響を与え、下位5%に位置する教員を、平均的な教員に置き換えるだけで、子どもの生涯収入の現在価値を、学級あたり2500万円も上昇させるそうです。
では、教員の質を高めるにはどうしたらよいでしょう。
教員研修などで教員の能力を高めるのが良いのか。それとも、そもそも能力の高い人を教員として採用することができるようにすべきなのか
正解は、後者。そもそも能力の高い人を教員として採用することができるようにすべき、だそうです。
教員免許は教育の質を担保しているわけではないのです。
運転免許が、自動車を運転するのに最低限必要な知識と技能を保証してだけで、運転が上手いことを担保しているわけではないのと同じということです。
小学校から大学までを単位制にしてはダメでしょうか?
習得には個人差があります。得意/不得意もあります。
一律で進む授業というのが、そもそも無理があります。
一方で、文科省は、科目ごとに到達目標を設けています。ならば、その目標に到達すれば良いわけです。
到達したら、単位を与える。それだけのことです。
少々古いですが、「平成7年度我が国の文教施策[第2部 第2章 第3節 2]」に面白いことが書かれています。
(2) 単位制高等学校
単位制高等学校は、誰でもいつでも高等学校教育を受けられるよう、単位制のみによる履修形態とした高等学校であり、多様な学習歴や生活環境を持つ学習者に対して、広く高等学校教育の機会を提供するものである。
単位制高等学校は、学年による教育課程の区分を設けないこととするとともに、入学・卒業時期に関する特例や多様な科目の開設と複数時間帯の授業実施などの特色を持っている。平成7年度現在、42都道府県に75校の国公立単位制高等学校が、7都府県に12校の私立単位制高等学校が設置されている。
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpad199501/hpad199501_2_093.html
文部科学省では、そうした教育を想定しており、その仕組みはすでに担保されています。
文科省の決意表明
いまの日本のICT教育、おかしいです
2020年6月1日の下記の記事は、衝撃的でした。

文部科学省の課長が苦言「いまの日本のICT教育、おかしいです」
5月11日に公開された文部科学省の「学校の情報環境設備に関する説明会」と題してライブ配信されたYoutube動画に対し、現場の教員たちから「よくぞ言ってくれた!」「素晴らしい!」と称賛の声が集まっている。
この動画から明確にわかるのは、「現場の教員がICT教育をやりたいと言っても潰してきた人たちがいた」という現実だ。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72974
勉強会などで多く聞かれたのは「ICTを取り入れようとしても管理職から潰されてしまった」という悲鳴のような声だった。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72974
ICTやオンライン学習というのは学びの保証に、当然ながら大いに役立つものです
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72974?page=4
『いや一律ではないからだめなんだ』というのは、やろうという取り組みから残念ながら逃げているようにしか見えません。(中略)是非、できることから進めてください。既存のルールにとらわれずに、臨機応変に
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72974?page=4
世の中が変わりました。GIGAスクール構想、新型コロナウイルスの感染症対策で世の中変わりました。ICTを使おうとしない自治体さんに説明責任が生じてきます。
文部科学省に対してではありません、全国の地元の自治体のお子さんがたに『なぜ使わないのか』という説明責任が生じるんだよということを、是非ご理解をいただいて、進めていただく必要があります。
(中略)
一般社会から見たら、教育のICT環境、ものすごく遅れています。私も教育担当して驚いています。みなさまもおかしいんだ、いまが間違っているのだとご理解いただいて是非対応してください。やろうとしてすすめられないんだったらご連絡ください。
https://gendai.ismedia.jp/articles/-/72974?page=5
やろうとしないということが一番子どもにとって罪だと思います
パラダイムシフトに対応できない教育者はご退場ください、と文科省が述べたことに、大きな意味があります。国はパラダイムシフトを求めているのです。
With コロナ/ After コロナ時代の大学教育の創造
2020年6月24日に文部科学省は高等教育に対しての、事実上の方針転換を目指すことを表明しました。

「大学教育のデジタライゼーション・イニシアティブ(Scheem-D)~ With コロナ/ After コロナ時代の大学教育の創造~」の実施について
大学(短期大学及び高等専門学校を含む。)の教育、とりわけ授業に焦点をあて、デジタル技術を上手に活用した特色ある優れた教育取組のアイデアを、大学教員やデジタル技術者(企業)が協働で、教育現場で実践、試行錯誤、普及・実装していく取組です。学修者本位の大学教育を実現するため、サイバーとフィジカルを上手に組み合わせて授業の価値を最大化する、「大学教育のデジタライゼーション」を目指します。
「大学教育のデジタライゼーション・イニシアティブ(Scheem-D)~ With コロナ/ After コロナ時代の大学教育の創造~」の実施について
キーコンセプトはいくつかあります。
MOOCsとAIによる質疑応答のみにより、高い学修到達度を達成(実証・実装) できる授業
VR(Virtual Reality)、AR(Augmented Reality)を用いた実習により、 現場実習、実験に近い経験を行える授業
アバター等を用いて学生同士の学びの場を創出、自主的な学びをい誘導する取組 将来的には、人間拡張技術(Human Augmentation)の活用なども 個別最適化の学び(Adaptive Learning)の実現
重要なのは、
目 的 ≠ デジタル技術を用いた授業をすること
大学教育のデジタライゼーション・イニシアティブ
目的 = デジタル技術を上手に活用して、圧倒的に高い学修到達度 の達成や、自発的な学び・気づきの効果的な誘導、現場実 習・実験に近い経験の機会確保など「授業の価値を最大 化」すること
これまで文部科学省は対面授業での教育を前提にしてきていましたが、初等教育に続いて、高等教育においても、対面授業ありきの方針を転換しようとしています。
放送大学という前例
そもそも、わが国には放送大学という前例があります。対面授業は前提としてない正規の大学で、卒業すれば学士が取得できます。つまり、文部科学省は、大きな声では言わないですが、対面授業を絶対とはしていないのです。
少々古いですが、「平成7年度我が国の文教施策[第2部 第2章 第3節 2]」において次のように書かれており、生涯学習の中核的機関として位置付けられています。
放送大学は、テレビ・ラジオの放送を利用して、大学教育の機会を広く国民に提供することを目的とし、昭和60年4月から、関東地域の一部を対象に放送の実施と学生の受入れを開始した。平成7年度第1学期には、約6万人の学生が学んでおり、7年3月までに6,679人の卒業生を送り出している。
放送大学は、入学試験を実施しておらず、また、多様な学習ニーズに対応できるよう、卒業を目指す全科履修生のほか、希望する科目のみを履修する選科履修生(1年間在学)、科目履修生(1学期間在学)、特定の事項を研究する研究生などの種別を設けている。
現在の放送対象地域は関東地域の一部に限定されているが、生涯学習の中核的機関として、国民の高度化・多様化する全国的な生涯学習ニーズに対応し、教育の機会均等を確保するため、放送衛星3号後継機を利用した、放送大学の全国化(対象地域の全国への拡大)の準備を推進することとしている。このため、各都道府県への 地域学習センター 【用語解説】の整備を行っている。
https://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/html/hpad199501/hpad199501_2_093.html
アダプティブ・ラーニング
Adaptive Learningとは個別最適化の学習です。究極的には、学ぶ人に応じたフルオーダーメイドの教育を提供する考えと言って良いでしょう。
効率的な習得方法は、人によって異なります。人から聞くのがいい人もいれば、自分で調べるのがいい人もいます。
そして、教育方法も様々にあります。最適な教育方法が一つだけでしたら良いのですが、様々な考えや経験、エビデンスに基づいて、百花繚乱の如く教育手法が提起されます。
こうなると、何がその人にとって最適なのかがわかりません。
しかし、現在では技術の進歩で、様々な教育手法を提供できる環境になりました。
ビッグデータとAIによって、その人に最適な教育方法が提供できる環境が整い始めています。
なお、アメリカではアクティブラーニングは下火です。
今は「反転授業」のほうが盛んになっています。
「反転授業」という手法のほうが盛んです。これは、生徒があらかじめ教材を学んだのちに授業に参加し、教室ではより高度なディスカッションなどを行うというものです。
https://mi-mollet.com/articles/-/29966?page=2
要するに、予習を前提に授業をするということです。
インプット(教える技術)
教える技術は様々あります。
ダイレクト・インストラクション(Direct instruction=DI)
I・エアーズ氏の「その数学が戦略を決める」にも書かれている手法です。
教師を脚本に従わせる手法です。そこに教師のオリジナリティが入る要素はありません。むしろ入れてはいけないのです。
DIの有効性についての証拠は一九六七年までにさかのぼります。
DIの有効性は圧倒的です。
読み、書き、算数、全てにおいて他の教育手法に勝り1位となりました。どんなモデルもDIに及ばなかったのです。
また、高次の思考力を要求される問題にも対応し、行間を読む能力にもたけていました。
つまり、いかなるモデルよりもDIに任せた方が、発想力豊かな子供になるということなのです。
DIのもっともすぐれているのは、誰にでもできるということです。
なぜなら、DIの授業は完全にマニュアル化されているからです。
マニュアル通りに動けば済むうえに、生徒の成績もあがる技法ですが、現場の教育者からは猛反発を食らいました。
教育を教師不要にしてしまうからです。
ですが、教師が不要になることに、何の不都合があるのでしょう?
教師は教えることから解き放たれて、別の役割を担えばいいのです。
学びのゲーミフィケーション
ゲームの要素を取り入れることで、効率的に学ぶ方法や、興味を惹きつける方法が研究されています。そうした記事の一つです。
ゲームによる学習は効率的で身に付きやすい

アウトプット(測定方法)
測定、つまりはテストですが、様々な方法があります。
CBT
Computer Based Testing(CBT)では、試験を全てコンピュータ上で行います。
場所や時間を選ばないメリットがあります。
知識の習熟度を測るだけであれば、最も効率的な方法の一つと考えられます。
懸念される不正も、何十万/何百万のパターンを用意することで、かなり抑止できます。
教諭/教師に求められる役割
やり抜く力
アンジェラ・ダックワース博士の「やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける」によると、教師にも賢明な教師、寛容な教師、独裁的な教師、怠慢な教師がいることがわかったそうです。
どんな教師よりも生徒の学力を伸ばすだけなく、生徒の満足度を高め、勉強に対する積極的な取り組みを促し、将来に大きな希望を抱かせるのは、賢明な教師でだそうです。
ちょっとした短いメッセージでも、相手のやる気を高めることができることも研究で明らかになっているといいます。
教わりたいのは、賢明な教師からです。他の教師は教育の現場からご退場頂く時代が来るのかもしれません。
教えるという仕事が、教諭/教師の仕事として比重が少なくなったら、どうなるでしょう。教諭/教師は不要になるのでしょうか?
いえ、そうではなく、役割を変えれば良いだけだと思います。
学生はティーチングアシスタントが実際には人間ではなくロボットだったことに気づかなかった

アメリカの研究者が人工知能を使ったティーチングアシスタント(TA)を導入して、オンラインでの学生に対応させたところ、誰一人としてTAがコンピューターだと気づかなかったケースが報告されています。
https://gigazine.net/news/20160509-ta-jill-watson/
教諭/教師に求められる役割を考えさせられる記事です。オンライン学習プログラムのTAをコンピューターに担当させるという実験を行い、誰ひとりTAがコンピューターだと気が付かなかったというのです。
約4万件分の学生からのメールやチャットを読み込ませて、質問や相談に対する応答方法を学習させました。
https://gigazine.net/news/20160509-ta-jill-watson/
つまり単純な質問などには、AIで十分対応可能ということなのです。24時間365日、学生の都合に合わせて、必要な回答がされる技術は可能になりつつあります。
単純な質問への対応が減ることにより、他の質問への対応の時間が生まれるようになるということです。
人に残されるのは、一般的な質問ではなく、特殊な個別の内容です。教諭/教師に求められるのは、そうした質問への回答ということになります。
実際の教室での講義に比べるとはるかに多くの学生に学習の機会を与えられるオンライン学習での最大の悩みは、学生から寄せられる大量の質問への対応であるとのこと。学生の質問の大半は、これまでにも、そしてこれからも何度も寄せられるであろう典型的な質問で、このありふれていて回答が決まっている質問への対応に、TAが忙殺されているという現状があるそうです。そのため、Jillのように典型的な質問や相談に対応できるロボットTAが実用化されれば、人間のTAにしかできない「より深い内容のやりとり」に「人間の」TAは集中することが期待でき、オンライン学習はより大きな成果を上げられると考えられています。
https://gigazine.net/news/20160509-ta-jill-watson/
示唆に富む記事
無慈悲に進むローエンド型の破壊的イノベーション
クレイトン・クリステンセン教授の「破壊的イノベーション」を引き合いに出した記事です。
「破壊的イノベーション」には2種類あります。
(A)市場がないと思われていた分野に需要を生み出して、既存市場を侵食する
(B)「性能が低くて安い」と思われていたものが、その低価格とシンプルさで、「過剰なサービス」で溢れる既存市場を侵食する
「やはり対面が一番」の裏で無慈悲に進むローエンド型の破壊的イノベーション
ここで考えないといけないのは、2番目の方だと言います。
なぜか?
わたしは、コロナによる強制的なオンライン授業から解放された先生たちの声を聞いていると同じような破壊的イノベーションが近づいているのを強く感じます。「私たちのサービスはオンラインなどには代替できないものだ」という思いは理解できます。しかし、
「オンラインでも十分だな」
という気づきが生まれ、既存のサービスから離れる層が相当数出てきます。そして、そこからいつのまにか
「オンラインのクオリティが急激に高まる」
というフェーズがやってくるのです。
「やはり対面が一番」の裏で無慈悲に進むローエンド型の破壊的イノベーション
「急場凌ぎ」の低い性能、つまりローエンド型の解決策がいつのまにか既存市場を破壊する可能性も大いにあります。既存プレイヤーが安心している足元で恐ろしいほどに静かに、無慈悲に進むのがこのローエンド型破壊的イノベーションの怖いところです。そして、破壊されるまで「状況を認めたくない」という思いも強いのが難しいところです。
「やはり対面が一番」の裏で無慈悲に進むローエンド型の破壊的イノベーション
アフターコロナに向けての動き
「withコロナ」時代の学校の「あり方」を模索する ミネルヴァ大学大学院と新渡戸文化学園の事例から

記事では結構エキセントリックな書き方もしていますが、10年後に見返せば、エキセントリックではないかもしれません。
教室で約40人が同時に黒板に向かって授業を受けるスタイルから見直さなければいけないし、1日6コマという「時間割」の概念すら障害となる。そもそも教員が「教える」という発想すら邪魔になるかもしれない。まさに一旦「常識」を脇に置いて、ゼロベースで「学校」あるいは「授業」を再定義する必要がある。
そのヒントを求め、教育ベンチャー株式会社トモノカイが、2つの事例についてのインタビューを行った。1つめは、100%の教育プログラムをオンラインで行うミネルヴァ大学大学院の実態。卒業生にヒアリングを行った。もう1つは、この機会をいち早く「学校改革」への推進力に変えた新渡戸文化学園の取り組み。こちらは教員に聞いた。
https://news.yahoo.co.jp/byline/otatoshimasa/20200623-00184261/
ネルヴァ大学は2020年時点で、世界で最も入りにくい大学と言われています。入学に関しては最難関の大学です。
キャンパスそのものが存在せず、授業はすべてオンライン。学部生は寮で共同生活を営むのだが、その寮も、世界7都市を移動する。学生は各地で地元企業やコミュニティでのインターンなどを経験する。「大学」の常識を覆す立て付けの、今世界で最も注目される大学だ。
話を聞いたのはミネルヴァ大学大学院を卒業した植山智恵さん。学部生とは違い、大学院生に寮はない。1回90分のオンライン授業が週に4コマあり、世界中から学生が参加する。時差もあるはずだが、遅刻は許されない。2分遅刻したら欠席扱いとなり、埋め合わせの課題が出される。
https://news.yahoo.co.jp/byline/otatoshimasa/20200623-00184261/
試験はない。毎回の授業への貢献度合い、アウトプット量がルーブリック形式で評価され、その積み重ねが成績となる。1回90分の授業のために学生たちは平均約4時間分にもなる事前課題をこなさなければいけないし、教員たちは一つ一つのオンライン授業の開発に多くの時間を費やしている。
インプットは事前に各自が行っておくのが大前提。授業はそれぞれの理解と思考と意見を持ち寄る場所というわけである。そのために、ミネルヴァ大学では、90分間の授業のうち、75%の時間を学生全員が活発に議論する時間に充てることになっている。残りの25%は授業の成果目標に関連する内容を話し合う時間に充てられる。ミネルヴァ大学では、1つのことを徹底的に考える時間を「Think through」と呼び、発想を広げる思考をする時間を「Far transfer」と呼ぶ。
https://news.yahoo.co.jp/byline/otatoshimasa/20200623-00184261/
ミネルヴァ大学大学院で教育を受けた経験を踏まえ、いま突然オンライン化を迫られている日本の学校において何をすべきだと思うか。植山さんの意見は以下だ。
「オンラインで何を実現するのかをまず選択する必要があるだろう。一気にミネルヴァ型を目指すのか、まずはあくまでも旧来の伝達型の授業の代替手段とみなすのか。どちらが正解という話でもない。それを選択した上で、生徒たちに対して協力してほしいことを明確化すべき。たとえば『反転学習にするので宿題を100%やってくるように。ただしわからなかったらわからないと質問していいですよ』というように、授業に臨む姿勢を具体的に示す必要があるだろう」
新しい学校の姿を実現するには、教員だけでなく生徒たちにも道標を示す必要があるという指摘だ。
https://news.yahoo.co.jp/byline/otatoshimasa/20200623-00184261/
教育をする側も、教育を受ける側も、意識の変革を迫られる時代になってくるということです。
学歴ということについて
大学進学率の現実
グローバルノート(東京都港区)の「世界の大卒比率 国別ランキング・推移(資料:Global Note、出典:OECD)」によると、下記のようになります。
日本の大卒比率が高い水準にあることが分かります。さらに進学率が伸びると考えるのか、鈍化していくと考えるのか、頭打ちと考えるのか…
第1位:カナダ(59.37%)
第2位:ロシア(56.73%)
第3位:日本(52.68%)
第4位:ルクセンブルク(51.64%)
第5位:イスラエル(50.25%)
第6位:韓国(50.03%)
第7位:アメリカ合衆国(48.34%)
第8位:アイルランド(47.31%)
第9位:イギリス(47.19%)
第10位:オーストラリア(47.13%)
第11位:フィンランド(45.93%)
第12位:アイスランド(45.04%)
第13位:スイス(44.41%)
第14位:ノルウェー(44.13%)
第15位:スウェーデン(43.97%)
第16位:リトアニア(43.15%)
第17位:エストニア(41.37%)
第18位:ベルギー(40.67%)
第19位:オランダ(40.39%)
第20位:デンマーク(40.35%)
第21位:ニュージーランド(39.07%)
第22位:スペイン(38.60%)
第23位:フランス(37.90%)
第24位:ラトビア(35.71%)
第25位:アルゼンチン(35.66%)
第26位:オーストリア(33.77%)
第27位:スロベニア(33.28%)
第28位:ポーランド(32.01%)
第29位:ギリシャ(31.89%)
第30位:ドイツ(29.90%)
学歴はどこまで必要
さまざまな教育手法が展開され、その結果として得られる学歴というものに対する一つの考え方です。

何人かの意見が書かれていますが、次の意見は興味深いです。
学歴そのものよりも、大学に合格するために「努力したこと」が重要です。例えばなにも努力しないで東大に受かる人は皆無です。つまり、『最大限の努力をして難関大学に合格する』という経験がある人は、ある程度のポテンシャルはあると考えていいと思います。
オンライン教育をめぐる記事
「オンライン授業の学習効果」は「対面授業」よりも低いのか?
「オンライン学習の効果」文献_200420

オンライン学習はなぜ 挫折してしまうのか

オンライン教育は大学の未来か?
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/publications/journal/no2/10.pdf
オンライン講義のMOOCが大学に取って代わることができない理由

そもそも日本の教育はダメなのか?
日本の教育は決して悪くありません。
京都大学大学院准教授のジェルミー・ラプリーさん、国立台湾大学准教授の小松光さんは「45歳から54歳までの学力は世界一で、日本の授業は海外からも高く評価されている。新しい教育法を無批判に取り入れるのではなく、教育現場の現実から学ぶべき」と言います。
https://mi-mollet.com/articles/-/29966?layout=b