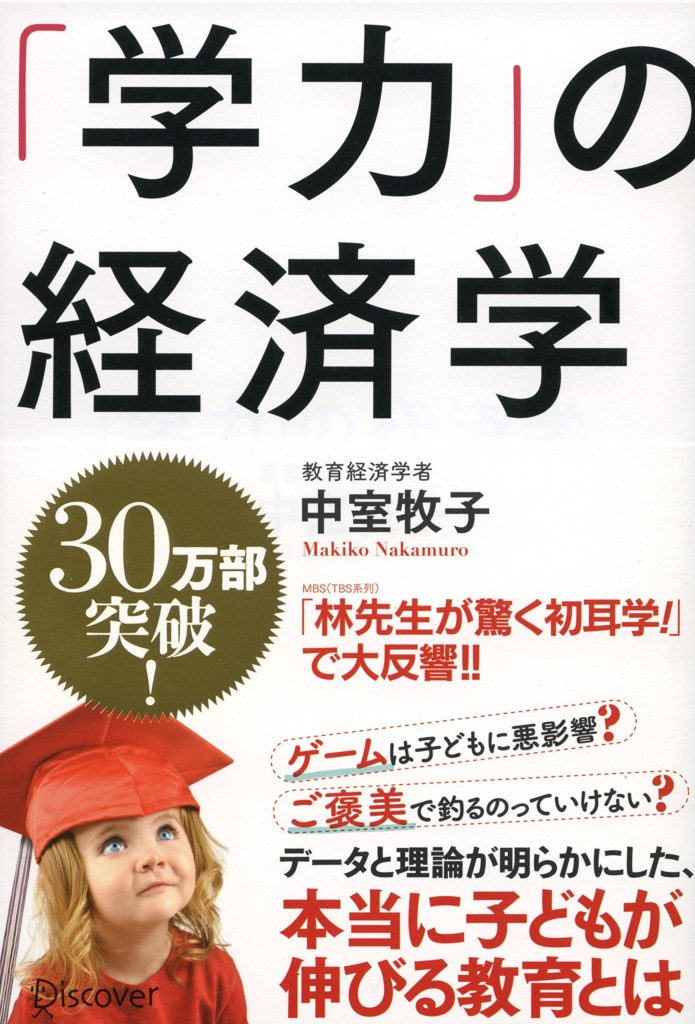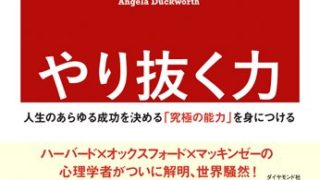この本について
面白い!とても面白い!
教育経済学は応用経済学の一分野だそうだ。
分析のために膨大なデータを使っての統計分析や、実験というのは、最近よく読んでいる行動経済学系でおなじみなので、ものすごくとっつきやすかった。
今まで、教育学者や学校の先生、塾の先生、子どもを有名大学に進学させた親の経験談、などで語られてきた「教育学」。
「個人的な経験」や「思いこみ」で語られてきた現実に、統計学的手法を用いて調査・分析した結果から読み解く「教育学」に光を当てたのが本書。
(それほど知られていないが、教育学を専攻する者(大学院の修士課程以上)であれば、統計学的な素養があって当たり前。純粋文系領域に思われているかもしれないが、統計学が理解できていない教育学者はニセ者である。)
著者の中室牧子さんは、慶應義塾大学総合政策学部の准教授。
慶応大学を卒業後、日本銀行に勤務。コロンビア大学の公共政策大学院に留学し、修士課程を修了。世界銀行で教育セクターの分析を担当したことが契機となって教育経済学に関心を持ち始め、再びコロンビア大の博士課程に戻り、教育経済学を学んだ。「エビデンスベーストの教育政策」を研究している。
本書は2015年6月に出版。
本書に 「エビデンス」という言葉が頻繁に登場する。証拠や根拠ということである。
本書では「科学的根拠」と書いているが、概念としては漢字から想起されるものよりも広いと思う。
そして、この用語は、なじみのある人と、そうでない人とでくっきり分かれると思う。
医療系や理系の人間にはなじみの深い人が多いのではないか。逆に文系の人間にはなじみのない用語だと思う。
だが、この概念は、急速に一般的なものになってきているので、ごく当たり前の日常用語になっていくものだと思う。
「エビデンス」。この単語は覚えておこう。
それらに基づいて、これまで常識として思われていたことが必ずしもそうではないことが示されている。詳細は本書に譲るが、かつての常識は、根拠のない迷信のたぐいだったりする。
(別の本になるが、記憶するということについても、従来の常識がどうやら間違っていることが分かってきているらしい。機会があったら、載せて行こうと思う。)
「エビデンス」で最も信頼されるものが「ランダム化比較試験に基づくもの」だそうだ。
エビデンスには階層があり、最も信頼度の高い順に次のようになっている。
1.ランダム化比較試験
2.非ランダム化比較試験
3.分析疫学研究(コホート研究やケース・コントロール研究など)…観察研究とも呼ばれる
4.症例報告…観察研究とも言われる
5.論説・専門家の意見や考え
ということで、データの「エビデンスのない教育本」はマユツバということである。
著者が有名だからといって、エビデンスに基づかない個人の経験をあたかも正解のように書いているものは、信用してはいけない。
なぜなら「専門家の意見が間違っている」可能性があるからである。
「専門家の意見が間違っている」という典型的な事例が「はじめに」で書かれている。
×ご褒美で釣っては「いけない」 → ○ご褒美で釣っても「よい」
×ほめ育てはしたほうが「よい」 → ○ほめ育てはしては「いけない」
×ゲームをすると「暴力的になる」 → ○ゲームをしても「暴力的にはならない」
【注意!】上記はとても単純化している。実際に書かれているのは、上記ほど単純ではない。上記だけだと、本書に書かれているニュアンスからズレて解釈をしてしまう人がいると思う。必ず、本書で確認してほしい。
例えば、『ご褒美で釣っても「よい」』というのは、心理学的な知見に基づく手法で、人間は遠い将来に貰える大きな褒美よりも、すぐに貰える小さな褒美の方に目がくらんでしまう性質を利用している。
具体的には、「テストでよい点を取ればご褒美」と「本を読んだらご褒美」とで比較した場合、「本を読んだらご褒美」の方が学力テストの結果が良くなった。
つまり、結果のアウトプットへのご褒美ではなく、インプットの段階でご褒美をあげるのが良いということが分かった。
そして、この褒美を与えたからといって、子どもの「勉強することが楽しい」という気持ちは消えなかったという。
例えば、『ほめ育てはしては「いけない」』というのは「むやみやたらに子どもをほめると、実力の伴わないナルシストを育てることになりかねません」ということにつながりかねないからである。
そうではなく「努力」をほめるのがよいという。努力をほめるのがよいというのは、いろんなところで聞くが、これもキチンとした「エビデンス」があるのである。
これまで語られてきた「努力」をほめるというのとは、個人的な経験などに基づくもので、根本的に意味合いが違う。
(『ゲームをしても「暴力的にはならない」』については、本書で確認してください)
本書で語られるのは、
経済学がデータを用いて明らかにしている教育や子育てにかんする発見は、評論家や子育て専門家の指南やノウハウよりも、よっぽど価値がある
ということである。
子育て中の家族や、これから子育てをしていく家族の必読の本だと思う。
上で書かれているように、評論家や子育て専門家の指南やノウハウよりも、よほど説得力がある。
そして、特に幼児期の子供を持つ家族は、ぜひ読むべきである。
その理由は、本書に詳しく書かれている。
目次
はじめに
第1章 他人の〝成功体験〞はわが子にも活かせるのか? - データは個人の経験に勝る
第2章 子どもを〝ご褒美〞で釣ってはいけないのか? - 科学的根拠に基づく子育て
第3章 〝勉強〞は本当にそんなに大切なのか? - 人生の成功に重要な非認知能力
第4章 〝少人数学級〞には効果があるのか? - エビデンスなき日本の教育政策
第5章 〝いい先生〞とはどんな先生なのか? - 日本の教育に欠けている教員の「質」という概念
第1章 他人の〝成功体験〞はわが子にも活かせるのか?
教育という分野に関しては、まったくといっていいほどの素人でも自分の意見を述べたがるという現象がしばしばおこる
これを評して「一億総評論家」状態だと述べている。
たしかにその通り。
珍現象にもかかわらず、誰もこの状態に違和感を覚えてこなかったことが、日本の教育に対する異常事態を端的に示している。
どこかの誰かかが子育てに成功したからといって、同じことをしたら自分の子供も同じように成功するという保証は、どこにもありません。
それにもかかわず、こうした「個人の体験記」を重宝してしまうところは、まさに「一億総評論家」が生み出した副産物なのだろう。
著者が嘆くのは
日本ではまだ、教育政策に科学的な根拠が必要だという考え方はほとんど浸透していないのです。
しかし、アメリカでは2000年代初めには、すでにこうした状況を脱しており、ブッシュ政権下で成立した「落ちこぼれ防止法」では111回も「科学的な根拠に基づく」というフレーズが使われており、エビデンスベーストポリシーが浸透しつつあるという。
ようするに、アメリカは
「どういう教育が成功する子供を育てるのか」ということを科学的に明らかにしようと
しているのである。
原因と結果、つまりは因果関係を明らかにして、教育政策を決めていくのが、今のアメリカである。
この因果関係には、いろいろな落とし穴がある。
その例だが。
文科省の「全国学力・学習状況調査」での分析で「親の年収や学歴が低くても学力が高い児童の特徴は、家庭で読書をしていること」とされている。
この1文で、次のように読み取ったら、間違っている可能性がある。
「子供に読書をさせるのが重要である」
この1文は、読書をしているから子供の学力が高い(因果関係)のではなく、学力が高い子供が読書を強いているに過ぎない(相関関係)可能性がある。
さらには、見せかけの相関の可能性もある。つまり、子どもに対する親の関心の高さが影響しているかもしれないのである。こうした親は子供に勉強を促すようにし、同時に本を買い与えるかもしれない。それが両方に影響を与えているかもしれない。
こうした可能性が考えられる中、どうしたらよいのか。
それが「統計学」を用いる手法である。
そのために、教育の分野で「実験」を行う必要がある。
この教育経済学の分野では、ノーベル経済学賞受賞者のゲイリー・ベッカー教授やジェームズ・ヘックマン教授をはじめとし、エスター・デュフロ教授、ラージ・チェティ教授、ローランド・フライヤー教授らが有名のようだ。
第2章 子どもを〝ご褒美〞で釣ってはいけないのか?
にんじんをぶら下げる
にんじんをぶら下げるということは、経済学でいうところの、インセンティブにどのように反応するかということにつながる。
そして
今ちゃんと勉強しておくのが、将来のためになる、というのは経済学的に正しい。
それは将来の収入を高めることにつながるからである。
人は、遠い将来のことなら冷静に考えて賢い選択ができても、近い将来のことだと、たとえ小さくともすぐに得られる満足を大切にしてしまう。
逆に言うと、目の前にご褒美をぶら下げられると、勉強することの利益や満足が高まり、それを優先することになる。
つまり「有効」ということである。
だが、「テストでよい点を取ればご褒美」と「本を読んだらご褒美」とではどちらが効果的か?
実験の結果、「本を読んだらご褒美」の方が学力テストの結果が良くなった。
結果のアウトプットへのご褒美ではなく、インプットの段階でご褒美をあげるのが良い。
アウトプットにご褒美を与える場合には、どうすれば成績を上げられるのかという方法を教え、導いてくれる人が必要
このご褒美作戦で心配なのは、インセンティブが失われることである。
だが、ご褒美によって、子どもの一生懸命勉強することが楽しいという気持ちは失わせなかった。
次に、ご褒美にふさわしいのは、何か?
子どもが小さいうちは、トロフィーのように、子どものやる気を刺激するような、お金以外のご褒美を与えるのがよいでしょう。
お金をご褒美に使うのも決して悪くはない。
ご褒美にお金を得た子供たちは、お金を無駄遣いするどころか、きちんと貯蓄し、堅実なお金の使い方をするそうである。
もっとも、貯蓄用の銀行口座を作って、家計簿を付けるなどの金融教育を同時に行っていたということのようだが。
ご褒美を習慣にすると子供にはよくないという研究
ご褒美を習慣にすると子供に何が起こる?
アメリカの大学の研究で分かったのは、親が物に依存した子育てをすると、その子が大きくなってからも物に依存した生き方をしやすいということ。親から頑張ったご褒美に「物」をもらって育った人は、大人になって物質依存症になりやすいのだそうです。
https://allabout.co.jp/gm/gc/451429/
今回の研究で悪影響と分かったのは3つのパターン。
1.モノで釣る…「100点を取ったら、あのゲームを買ってあげる」:なんらかの達成と関連づけたご褒美の場合
2.愛情表現:親の愛情表現として物を買ってあげる場合
3.罰則:罰則として、子供の好きなおもちゃを取り上げる場合
そして、物質的なご褒美は
1.どんどんエスカレートすること
2.効果や満足感に持続性がないこと
がわかってきたという。
で、どうするか
子育て心理学的に見ておすすめの「やる気アップ」は、ご褒美ではなく、物を介さない「ほめ」。
子どもはほめて育てるべきなのか
子どもたちの自尊心を高めれば、学力や意欲が高まり、反社会的行為を未然に防ぐことができるのではないかという期待のもと行われた実験。
結果は
自尊心が高まれば、社会的なリスクから遠ざけることができるという有力な科学的根拠は、ほとんど示されなかった。
実は
自尊心と学力の関係は相関関係にすぎず、因果関係は逆だった。
つまり、学力が高いという「原因」が、自尊心が高いという「結果」をもたらしていた
そして、子どもたちの自尊心を高める取り組みは、ときに学力を押し下げる効果をもつ
ほめても、成績は決してよくすることはない
むやみやたらに子どもをほめると、実力の伴わないナルシストを育てることになりかねません
ほめ方
頭がいいねのね、ともともとの能力(頭の良さ)をほめると、子どもたちは意欲を失い、成績が低下する。
そうではなく「努力」をほめる
「よく頑張ったわね」と努力した内容をほめられた子供たちは、テストでも粘り強く、挑戦を続ける。
テレビやゲーム
研究の多くは、テレビやゲームそのものが子供たちにもたらす負の因果効果は、考えているほど大きくはない
そして、テレビやゲームをやめさせても学習時間はほとんど増えない
男子で最大1.86分、女子で最大2.70分増加するに過ぎない
1日1時間程度、テレビやゲームをすることで息抜きすることに罪悪感を覚える必要はない
一方、2時間を超えると、子どもの発達や学習時間への負の影響が飛躍的に大きくなることも明らか
勉強させるには
勉強するように言うのは、逆効果で、効果がない
しかし
「勉強を見ている」または「勉強する時間を決めて守らせている」という、親が自分の時間を何らかの形で犠牲にせざるを得ないような手間暇のかかるかかわりというのは、かなり効果が高い
そして
男の子なら父親が、女の子なら母親がかかわるとよい
友達が与える影響
学力の高い友達の中にいると、自分の学力にもプラスの影響がある。しかし、必ずしもこれが正しいわけではなく、自信を失わせてしまうこともある。
問題児の存在が、学級全体の学力に負の因果関係を与える
最近の研究では、習熟度別学級は、ピア・エフェクトの効果を高め、特定の学力層の子供たちだけでなく、全体の学力を押し上げるのに有効な政策であることがわかってきた
しかも、これは学力の低い子供たちに特に有効である
注意点がある。
学齢が低いときに実施してしまうと、格差が拡大して、平均的な学力が下がってしまう
負のピア・エフェクトがあまりにも大きい場合、親はどうすればいいか。それは、思い切って引越しをしてしまうことも選択肢である。
教育にはいつ投資すべきか
もっとも収益率が高いのは、子どもが小学校に入学する前の就学前教育(幼児教育)です。
だが、これはイコール学習塾ではなく、しつけなどの人格形成や、体力や健康などへの支出も総合的に含んだ「人的資本」への投資が大事ということである
近年、「非認知能力」に注目が集まっている。
忍耐力、社会性、意欲的といった、人間の気質や性格的な特徴のようなものを指す言葉。「生きる力」のようなものだという。
「非認知能力」が高いほど、将来の年収、学歴や就業形態などの労働市場における成果にも大きく影響することが明らかになってきたそうだ。
この「非認知能力」はIQとは別物である。
子どもへの投資は、この「非認知能力」を育てるために使うべきで、結果として「しつけ」や、「体力」や「健康」などへの支出が適正ということになる。
第3章 〝勉強〞は本当にそんなに大切なのか?
小学校前のIQが高まったとしても、その効果は長続きはしない
こうしたIQや学力テストで測れる能力を「認知能力」という
一方で
「非認知能力」と呼ばれるものがある。
忍耐力があるとか、社会性があるとか、意欲的であるといった、人間の気質や性格的な特徴のようなものを指し、「生きる力」のようなものである
この「非認知能力」が、
将来の年収、学歴や就業形態などの労働市場における成果にも大きく影響することが明らかになってきたのです。
重要な非認知能力
自制心 … 有名なマシュマロ実験
筋肉のように鍛えるとよいと言われる
つまり、継続と反復である
やりぬく力(GRITとも呼ばれる)
心の持ちようが大切
能力は生まれつきのものではなく、努力によって後天的に伸ばすことができると信じる子はやりぬく力が強い
親や教師から定期的にそのようなメッセージを伝えられた子は、しなやかな心を手に入れ、やりぬく力が強くなる
※ アンジェラ・ダックワース教授の「やり抜く力 GRIT(グリット)――人生のあらゆる成功を決める「究極の能力」を身につける」がとても参考になります。
しつけ
4つの基本的なモラル
- 嘘をついてはいけない
- 他人に親切にする
- ルールを守る
- 勉強をする
しつけの一環として親から教わった人は、全く教わらなかった人と比較すると、年収が86万円高いそうだ
非認知能力への投資
非認知能力への投資は、子どもの成功にとって非常に重要であることが多くの研究で示されています。
人生のかなり長い期間にわたって計り知れない価値を持つ非認知能力
最近では非認知能力を鍛える手段として、部活動や課外活動に注目が集まっているそうだ
社会奉仕活動やアウトドア活動なども有効であるといわれている。
第4章 〝少人数学級〞には効果があるのか?
少人数学級は費用多効果が低い
たしかに少人数学級には学力を向上させる因果関係はあるのだという。
だが、少人数学級は他の政策と比較すると費用対効果は低い政策であることが明らかになっている。
もっとも効果が高いのは、教育を受けることの経済的な価値を教えることだという。
お金のかからない政策で、少ない費用で高い効果を発揮する政策だそうだ。
これを中室先生は次のように説明するそうだ。
高校を卒業後すぐに働き始めた人と、大学を卒業してから働き始めた人の間では、生涯で稼げるお金に、実に1億円の差があります。(中略)宝くじで1億円当たることを夢見なくても、大学へ行けば生涯で稼げるお金は1億円高くなるのですよ。
日本で実施されてきた「少人数学級」や「子ども手当」は、学力を上げるという政策目標の点からは、費用対効果が低いか効果がない、ということが海外のデータを用いた政策評価の中ですでに明らかだそうだ。
少人数学級の費用対効果が低い、ようは「意味がない」ということは、海外などの研究成果などから明らかなのだというから、これにこだわる政治家、役人、学者、教育関係者は、勉強をしてもらいたいものだと思う。
もっとも効果が高いのは、教育を受けることの経済的な価値を教えることだという。
具体的な話が載っている。中室准教授は次のように話をするのだという。確かに、こうした話は、極めてリアリティがあって、何とかしなければならないと思わせるのに十分だ。
だったら、
やめようよ。
そして、続けると、
巨額の財政赤字を抱えている日本で、「少人数学級になるときめ細かい指導ができる」などという根拠のない期待や思い込みで、財政支出を行うのは極めて危険
だという
それなら、
絶対にやめろ!
「35人学級問題」をめぐるエビデンス無き不毛な議論
「35人学級問題」をめぐる財務省と文科省のエビデンス無き議論 【特別対談】慶應義塾大学・中室牧子准教授

教育分野における「エビデンスベースト」の重要性を説き、注目を浴びる気鋭の経済学者・中室牧子氏
この「エビデンスベースト」はこれからとても重要。
リテラシーの一つと言っていいと思う。
で、文科省と財務省とで繰り広げられたのが、お粗末な空中戦。
中室 昨年、小学校の少人数学級に関する議論が話題に上りました。「1クラス35人の少人数学級を継続すべきか、(元の)40人学級に戻すべきか」という議論で、財務省は「40人学級に戻してコストを削減すべき」、文部科学者は「35人学級を維持すべき」と、両省の主張が真っ向から対立しました。財務省は35人学級の廃止によって、約86億円のコスト削減につながると主張していました。少人数学級をやめればコスト削減につながるのは事実ですが、その根拠として財務省が提示した 「エビデンス」は、あまりにも不十分なものでした。
西内 へえ、どんなエビデンスだったんですか?
中室 35人学級は、2011年に公立小学校の1年生に対してのみ導入されました。財務省は、2011年以前と以後で、いじめ、暴力行為、不登校の平均値を比べると、いじめや暴力、不登校には大きな変化が見られないので、少人数学級には効果がない。したがって、「40人学級に戻すべき」と主張したのです。
中室 OECDが実施している「国際教員指導環境調査(TALIS)」という調査の結果を根拠にしています。しかし、日本では労働者の労働時間は教員に限らず長いので、多忙感があるからといって公務員である教員を増加させることが果たして正当化されるのでしょうか。このように省益の異なる2つの議論が出てきたときに、海外では、エビデンスによって決着が図られるはずなのです。ところが日本の場合、どちらの主張にも科学的な根拠がなく、互いに「こうあるべきだ」という主張を繰り返すだけになってしまっています。
西内 互いに根拠を持たないから、地に足をつけた論争にならないわけですね。
平等主義が格差を拡大させる
家庭の資源に格差がある中で、すべての子供に同じ教育を行えば格差が拡大していく
研究でわかっているのは
ある世代の子供全員を対象にして平等に行われた政策は、親の学歴や所得による教育格差を拡大させてしまうことがある
貧困の世代間連鎖は断ち切らなければならない
しかし
家庭の資源の不足に対処するために、親への所得移転を行えばよいかというとそういうわけではない
「子ども手当」のような補助金は学力の向上には因果関係を持たなかったことが明らかにされています。
また
学校で平等を重視した教育―「手をつないでゴールしましょう」という方針の運動会など―の影響を受けた人は、他人を思いやり、親切にし合おうという気持ちに「欠ける」大人になってしまうことが明らかになっています。
第5章 〝いい先生〞とはどんな先生なのか?
いい先生
遺伝や家庭の資源など、子ども自身にどうしようもないような問題を解決できるポテンシャルを持つのは、「教員」である。
では、「いい先生」とはなにか?
授業評価では正しく教員の質を測ることができているか不明である。
ある研究では、美人の先生の方が授業評価が高かったという、身もふたもない結果が出ているそうだ。
教員が担当した子供の成績の変化で見るというではどうだろうか。
学力の変化を「付加価値」と呼ぶ
アメリカでは教員の質を測る指標として「付加価値」が一般化している
そして研究では
付加価値が教員の質の因果効果をとらえるのに、きわめてバイアスの少ない方法である
ことが明らかにされたそうだ。
付加価値で見たとき、
下位5%に位置する教員を、平均的な教員に置き換えるだけで、子どもの生涯収入の現在価値を、学級あたり2500万円も上昇させる
ことができるそうだ。
これって、すごくない?
となると、教員の質を高めるにはどうしたらよいのか?
教員研修などで教員の能力を高めるのが良いのか。
そもそも能力の高い人を教員として採用することができるようにすべきなのか
正解は、後者。
そもそも能力の高い人を教員として採用することができるようにすべきである
教員の給与を上げても、教員の質が高まり、子どもたちの意欲や学力改善につながるというエビデンスは決して多くない
成果主義が教員の質の向上に役に立たない理由はよくわかっていないそうだ。
ただ、与え方によっては質を上げられる可能性はあるという
それは、付加価値の上昇が認められなかった場合、一度支払われたボーナスを返さなければならないという「失う」ということをした場合、上昇がみられたという。
さて、前に話を戻すと
教員研修が教員の質に与える因果効果はないという結論が優勢
そして、
すでに教壇に立っている教員の質を高めるために、どのような政策が有効かという問いに対しては、教育経済学では明快な答えを持たない
だが、
教員の質を上げる方法はある。
もともと能力の高い人を採用すればよい。
そのためには
教員になるための参入障壁をなるべく低くする、つまり教員免許制度をなくしてしまう
教員免許を持っているからといって、教員の質の保持・向上に因果効果があるとは言えない。
研究によれば、教員免許の有無による教員の質の差はかなり小さいというのがコンセンサスである。
つまり、極論すれば、ダメな先生はダメなまま、ということである。
ダメな先生には退場して頂くのが、子どもたちのために良いということになる。
下位5%に位置するダメな先生に教わりつづけると、1クラスあたり、生涯収入の現在価値2500万円分の上昇の機会をうしなうことになる。
ようするに、教員免許は質を担保していない。
参考記事
「子供の学歴」「英語力」「教育費」の真の関係

幼児期の非認知スキルが大事だとのこと。
幼児期の教育によって身につけたスキルは、その後の学習を効率的にし、継続しやすくすると主張しています。就学前に十分なスキルを獲得しておけば、就学後の教育効果が大きくなるというわけです。これを経済学では「教育投資の動学的補完性」と呼んでいます。
https://forbesjapan.com/articles/detail/32305/1/1/1
非認知スキルとは次のようなもので、GRITなども含まれるようです。
IQや学力テストで計測される認知スキルとは区別して用いられ、「忍耐力がある」「社会性がある」「意欲的である」など、人それぞれの気質や心理的な特徴のようなものを指します。
https://forbesjapan.com/articles/detail/32305/1/1/1